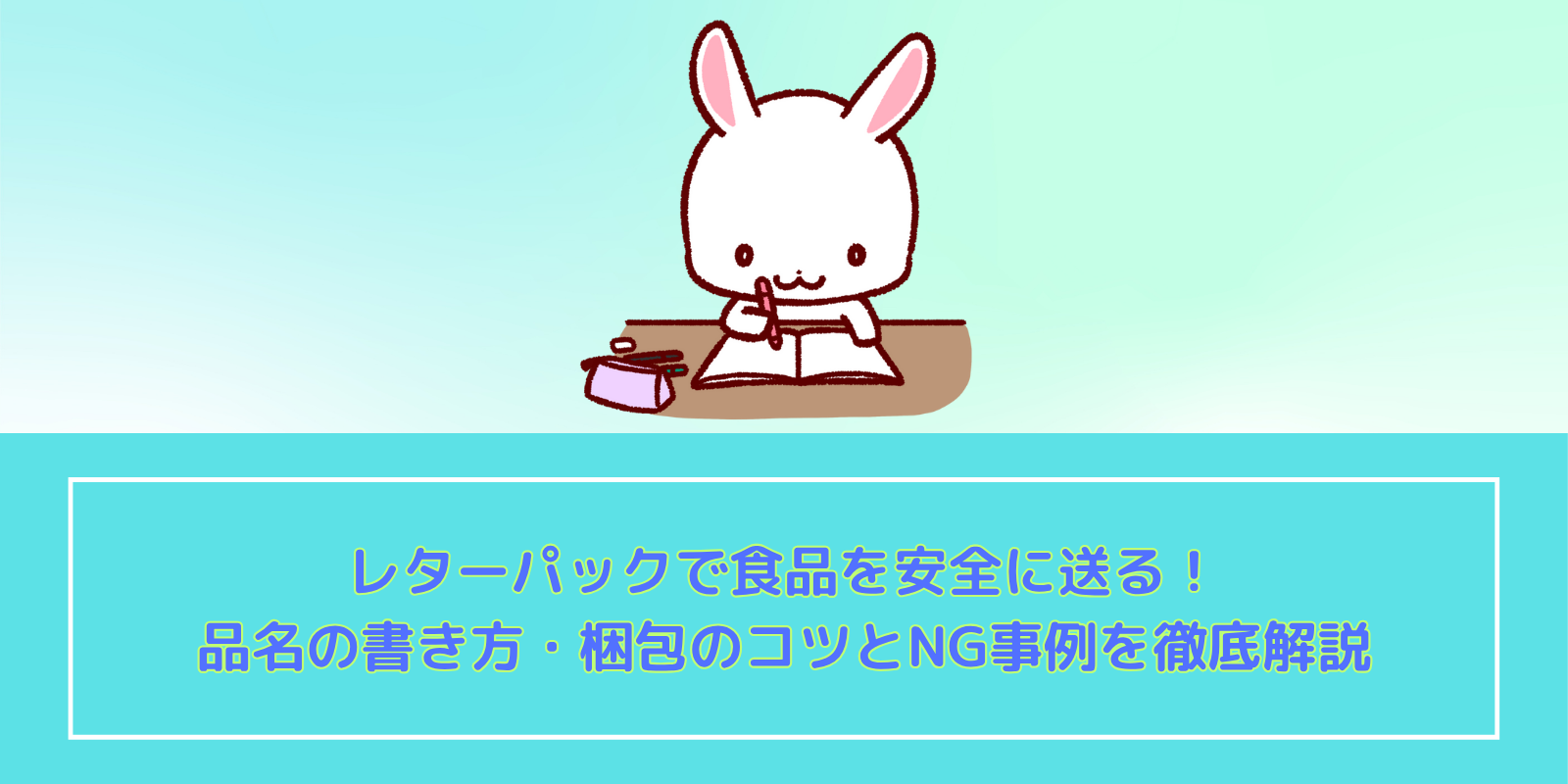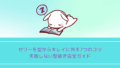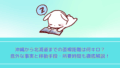「大切な人に手作りのお菓子を送りたい」「実家の母に地元の味を届けたい」…そんなとき、気軽に使えるレターパック。でも、「食品って本当に送れるの?」「品名はどう書けばいいの?」と、心配や疑問が次から次へと浮かんできますよね。
実は、レターパックで食品を送るときには守っておきたいルールやマナーがいくつかあります。宛名や品名の書き方、梱包のコツ、どんな食品なら送れるのか…。ネットで調べても情報がバラバラで、「結局どうすれば?」と迷ってしまう人も多いんです。
この記事では、あなたの「どうすれば?」にしっかり寄り添いながら、レターパックで食品を送るときの正しい品名の書き方や梱包方法、絶対に押さえておきたい注意点を、実体験とともに詳しくまとめました。送る人も受け取る人も、安心して気持ちを届けられるコツをたっぷり詰め込んでいます。
読み終わるころには、「これなら大丈夫!」と自信を持ってレターパックで食品を送れるようになりますよ。あなたの想いが、ちゃんと相手に届きますように。ぜひ最後までじっくり読んでみてくださいね。
レターパックで食品を送る際の正しい書き方と注意点まとめ
レターパックで食品を送る際の正しい書き方と注意点まとめについて解説します。
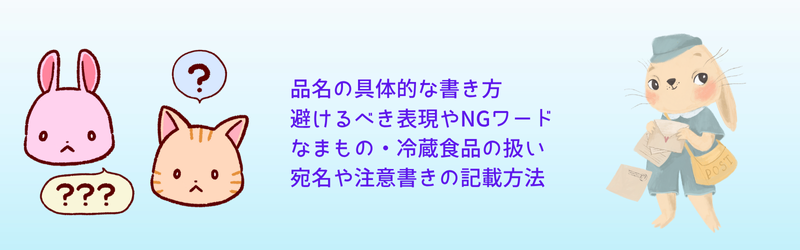
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
品名の具体的な書き方
レターパックで食品を送る場合、まず重要なのは「品名」の書き方です。
基本的には「食品」や「お菓子」と記載してOKですが、より具体的に「クッキー」「チョコレート」「焼き菓子」など内容物がわかる表記がおすすめです。
具体的な品名を書くことで、郵便局スタッフにも受取人にも内容が伝わりやすくなります。
たとえば「食品(クッキー)※なまものではない」や「お菓子(チョコレート)※常温保存可能」など、補足も添えるとより安心ですね。
筆者も実際にレターパックで焼き菓子を送ったことがありますが、「食品(焼き菓子)※なまものではありません」と書いたら一度もトラブルになったことがありませんでした。
書き方に悩んだら、「食品(具体名)」+「なまものではない」「常温保存可能」などの補足をセットにしましょう。これは本当におすすめです!
避けるべき表現やNGワード
品名を書くときに「プレゼント」「ギフト」「食品類」といった曖昧な表現は絶対にNGです。
これらは中身が特定できないため、郵便局で内容確認や書き直しを求められる場合があります。
実際、「ギフト」とだけ書いたことで窓口で差し戻しになった…という声もSNSや知恵袋でよく見かけます。
トラブルを避けるためにも、必ず具体的な品名を記載しましょう。
また、「食品類」とだけ書いても内容が特定できないため、やはり具体的な食品名を書くのがベストです。
「どう書けばいいかわからない…」という方は、前述の具体例を参考にしてくださいね。
なまもの・冷蔵食品の扱い
レターパックでは生ものや冷蔵・冷凍が必要な食品は送れません。
具体的には生肉・生魚・生菓子・冷蔵プリン・生クリーム入りケーキなどが該当します。
また、冷蔵・冷凍が必要なものは、配送中の温度変化や管理が難しいため、郵便局でも受け付けてもらえません。
安全のためにも、必ず常温保存可能で、腐敗や劣化の心配がない食品を選びましょう。
「えっ、これもダメなの?」と不安になる場合は、郵便局の公式サイトや窓口に確認するのがおすすめです。
とにかく「なまもの」「冷蔵冷凍が必要」なものはNG!と覚えておけば間違いありませんよ。
宛名や注意書きの記載方法
レターパックの表面に書く宛名は通常通りでOKですが、品名記載欄にきちんと食品名を書くことが大切です。
また、品名の後に「※なまものではありません」「※常温保存可能」といった注意書きを添えると、郵便局スタッフの安心感にもつながります。
相手に伝えたいことがある場合(例:開封後は早めにお召し上がりください等)は、メモやシールで追加するのも親切ですね。
ちょっとした配慮で、送り先とのトラブルもぐっと減ります!
宛名や品名、注意書きもセットで考えると失敗しませんよ~。
レターパックで送れる食品と送れない食品を徹底解説
レターパックで送れる食品と送れない食品を徹底解説します。
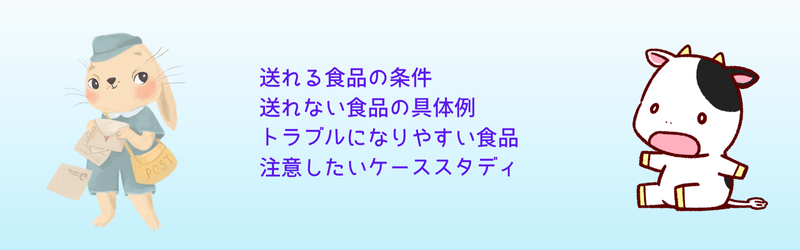
食品を送る前に、何がOKで何がNGか、しっかり確認しましょう!
送れる食品の条件
レターパックで送れる食品の条件は、ズバリ「常温保存できて腐らないもの」「液体が漏れ出さないもの」「密封できるもの」です。
たとえばクッキー、パウンドケーキ、チョコレート、スナック菓子、キャンディ、乾物、インスタント食品などが代表的な例です。
とくに「なまものではない」「冷蔵・冷凍不要」「配送中に崩れたり、漏れたりしない」ことが大事です。
実際に郵便局の公式サイトにも、「レターパックで生ものや冷蔵・冷凍食品は送れません」と明記されています。
もし悩む場合は「賞味期限が長め」「配送に2日ほどかかっても傷まない」ものを基準に選んでくださいね。
簡単な表でまとめると、下記の通りです。
| 送れる食品 | 理由・注意点 |
|---|---|
| クッキー・焼き菓子 | 常温OK・密封しやすい・壊れやすいので梱包はしっかり |
| チョコレート | 常温保存が前提・夏は溶けやすいので注意 |
| スナック菓子 | 密封袋入りならOK・つぶれやすいので工夫必須 |
| キャンディ・飴 | 個包装・常温保存OK・溶けやすいものは避ける |
| 乾物(昆布・煮干し・干し椎茸など) | 長期保存OK・密封必須 |
| インスタント食品 | 未開封パック・液漏れしないもの |
このあたりを意識して選べば、トラブルはまず起きませんよ!
送れない食品の具体例
一方、レターパックで送れない食品には明確なルールがあります。
生肉・生魚・生クリームを使ったケーキやシュークリーム、冷蔵・冷凍食品全般、刺身や漬物など、配送中に腐る・傷むリスクのあるものはNGです。
また、液体(味噌汁・ジュース・ヨーグルトなど)は、密封しても漏れる可能性が高いため不可。
手作りの生菓子や未包装のお惣菜も、食中毒リスクがあるので避けましょう。
郵便局の窓口で「これは送れません」と言われてしまうケースも実際に多いので要注意!
ざっくりまとめると…
| 送れない食品 | 理由・注意点 |
|---|---|
| 生肉・生魚 | 腐敗・食中毒リスクあり・冷蔵必須 |
| 生クリーム系ケーキ | 冷蔵必須・配送中に崩れる |
| 刺身・漬物 | 腐敗リスク・液漏れ危険 |
| 未包装惣菜・手作り弁当 | 衛生・保存上の問題 |
| 冷蔵・冷凍食品 | 常温で劣化・NG |
| 味噌汁・ジュースなど液体 | 密封しても漏れる可能性大 |
送れるか不安なものは、必ず郵便局のサイトや窓口で確認を!
トラブルになりやすい食品
「送れる食品だけど、実はトラブルになりやすい」ものも存在します。
たとえば夏場のチョコレートや、つぶれやすいスナック菓子などは、届いたときに溶けていたり、粉々になっていることも。
また、密封不足の焼き菓子や乾物は、香りが漏れて封筒の外まで広がる…なんてこともあります。
筆者も以前、パウンドケーキを送りましたが、緩衝材不足で一部がボロボロになってしまいました。
「大丈夫だろう」と思ってもしっかり梱包・防水・密封して、配送中のダメージを最小限に抑えましょう!
トラブルを避けるには、下記のような工夫がおすすめです。
- チョコは夏場を避けて発送
- スナック菓子は個包装に分ける
- 香りが強い食品は二重袋で密封
一手間かけるだけで、届いたときのガッカリを防げますよ。
注意したいケーススタディ
実際によくある「やっちゃった…」な事例も紹介します。
・「ギフト」と書いて窓口で差し戻された
・焼き菓子が配送中につぶれてボロボロになった
・密封が甘く、封筒の中がベタベタに…
・夏場にチョコレートを送って全部溶けてしまった
こうした失敗談はネットにもたくさん載っています。
送る前に「自分だったらどう受け取ってほしいか」を考えたり、「ちょっと過剰かな?」くらいしっかり梱包することが安心につながります!
困ったときは公式サイトや郵便局員さんに相談すると確実です。
経験談や失敗談も参考に、安心して食品を送りましょう!
レターパックで食品を安全に送る梱包方法7選
レターパックで食品を安全に送る梱包方法7選をまとめます。
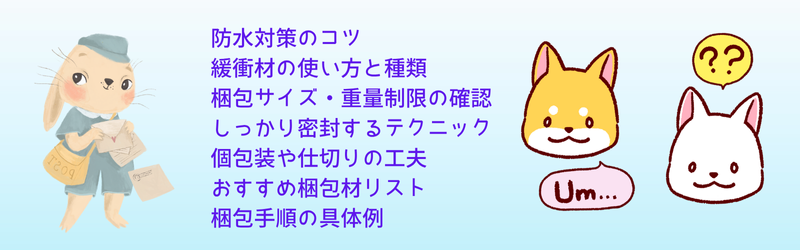
ひと手間かけるだけで、食品の破損・水濡れ・型崩れリスクをグッと減らせますよ!
防水対策のコツ
レターパックの専用封筒は防水性がありません。
そのため、食品は必ずビニール袋やチャック付き袋、OPP袋などで包み、湿気や雨から守りましょう。
もし食品に油分や粉がある場合も、袋に入れることで外袋への付着を防げます。
ビニール袋はできれば二重にするのが安心です。
封筒の外側に防水スプレーをサッと吹きかけるのも一つの工夫です。
以前、手作りクッキーを送った際に大雨の日が重なり、外袋に染みができたことがありました。
中身はビニール袋で守られていたので無事でしたが、「ここまでやる?」というくらいの防水対策が大切ですよ!
緩衝材の使い方と種類
割れやすい食品(クッキーや焼き菓子、チップスなど)は、プチプチ(気泡緩衝材)やクッション封筒、エアークッションでしっかり守りましょう。
隙間があると配送中に食品が動いて壊れやすくなります。
新聞紙やクラフトペーパー、キッチンペーパーも意外と使えます。
ただし、緩衝材を詰めすぎて封筒の厚み制限を超えないよう注意!
「もったいないかな?」と思っても、無事に届けるためには必須の工夫ですよ~。
手作りお菓子を送った経験から言うと、プチプチ+内箱のW使いが最強です!
梱包サイズ・重量制限の確認
レターパックライトは「厚さ3cm以内・4kgまで」、レターパックプラスは「A4サイズ・4kgまで」という制限があります。
プチプチや内箱、仕切りを使うとつい厚みオーバーしがちなので、必ず封筒に入れてみて厚みを確認しましょう。
サイズや重さを超えると、受け付けてもらえなかったり、追加料金が発生する場合があります。
家庭用のはかりや、厚さ測定定規があると便利です。
梱包材でパンパンになって「入らない!」と焦った経験もありますので、事前にチェックが超大事です!
しっかり密封するテクニック
梱包の最後は「しっかり密封」すること。
食品が入った袋の口はしっかりテープやタイで止めて、空気や湿気、虫が入り込まないようにしましょう。
レターパックの封筒の口も、しっかりとノリ付けやテープでふさぐと安心です。
配送中に封が開いてしまうと中身が飛び出してしまうので、念には念を入れて密封してくださいね。
以前、封筒の口が少しだけ開いていて「中身が飛び出してた」と言われたことがあるので、最後の一押しを忘れずに!
個包装や仕切りの工夫
お菓子や食品をそのまま封筒に入れるのではなく、個包装にしたり仕切りを設けるのも有効です。
チョコや飴などは小分け袋に入れ、ぶつかり合わないようにすることで破損を防げます。
段ボールや厚紙で仕切りを作って入れると、よりしっかり守れます。
また、食品同士が擦れて傷んだり、香りが移るのも防げるのでおすすめです。
筆者も仕切り用の厚紙をよく使いますが、簡単なのに効果抜群ですよ!
おすすめ梱包材リスト
実際に使って便利だった梱包材をリストアップします。
- チャック付きビニール袋(食品密封+防水)
- OPP袋(お菓子の個包装に最適)
- プチプチ(割れやすいものの必需品)
- クッション封筒(緩衝+簡単梱包)
- 段ボール・厚紙(仕切りや補強に)
- 新聞紙・クラフトペーパー(隙間埋め)
- 耐水スプレー(封筒の外側防水に)
これらを組み合わせれば、どんなお菓子も安心して送れます!
梱包手順の具体例
実際にレターパックでお菓子を送る場合の梱包手順をまとめます。
- 食品を個包装・ビニール袋・OPP袋に入れて密封
- 割れやすいものはプチプチで包む
- 必要に応じて内箱や厚紙の仕切りを使う
- 封筒に食品と緩衝材を入れて、隙間を埋める
- 封筒の口をしっかりテープやノリで閉じる
簡単そうに見えて、実はひと手間が大事なんです。
「これでもか!」というくらい丁寧に梱包してあげてくださいね。
水濡れ・破損防止のための最適梱包材とその活用法
水濡れ・破損防止のための最適梱包材とその活用法について解説します。
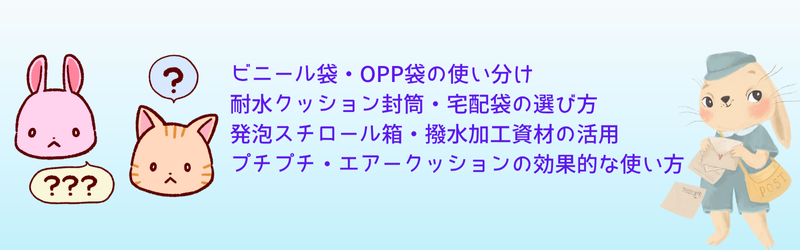
どの梱包材をどう使えば「水濡れゼロ・割れゼロ」に近づけるのか、詳しく見ていきましょう!
ビニール袋・OPP袋の使い分け
まず、水濡れ防止の基本は「袋で包む」こと。
チャック付きビニール袋は、密閉性が高く食品やお菓子の防水に最適です。
個包装にしたい場合は、透明で強度のあるOPP袋が使いやすいですよ。
特に、粉ものやパウダー系のお菓子には二重袋にすることで万が一の破損にも安心です。
OPP袋は封をテープで止めるとより防水効果がアップします。
コストも安く、100円ショップでも手に入るので、まず用意しておきたいアイテムです!
耐水クッション封筒・宅配袋の選び方
外装の防水を強化したいなら、耐水タイプのクッション封筒や宅配袋が効果的。
特に梅雨時期や冬の雪の日などは、雨や結露で封筒が湿るリスクがあるのでおすすめです。
内側がプチプチになっている「クッション封筒」は、衝撃吸収と防水性を兼ね備えた優れモノ。
ビニール素材の宅配袋は、強度も高く破れにくいので、外装用として1枚被せて使うのもアリです。
筆者も、雨が降りそうな日は必ず外装にビニール宅配袋を使っています。実際にトラブルを防げたので安心感がありますよ!
発泡スチロール箱・撥水加工資材の活用
さらに徹底した水濡れ防止には、発泡スチロール箱や撥水加工ダンボール・紙袋が活躍します。
発泡スチロール箱は特に保冷や強い耐水が必要な場合に重宝しますが、サイズや厚みがレターパック規定内に収まるように注意が必要です。
撥水加工ダンボールや紙袋は、長時間の雨や湿気にも強く、他の梱包材と組み合わせることでさらに防御力アップ。
実際、旅行のお土産を送る際など、外装を撥水タイプで覆うと安心です。
外箱はなるべく軽量で薄型のものを選ぶのがコツです!
プチプチ・エアークッションの効果的な使い方
割れやすい食品・お菓子には、プチプチ(気泡緩衝材)が最強の味方。
包むだけでなく、内箱の中に巻いたり、隙間を埋めるのにも使えます。
エアークッションは空気の層で衝撃を吸収し、割れやすいものでも安心して送れます。
食品と一緒に箱の四隅や上下にプチプチを敷くと、配送中の揺れや落下ダメージをしっかりガードしてくれます。
緩衝材はケチらず使うのがポイント!お菓子を潰さず届けたいなら、「包む」「敷く」「詰める」この三段構えで防御してくださいね。
レターパックで食品を送る時によくある質問5選
レターパックで食品を送る時によくある質問5選をまとめて解説します。
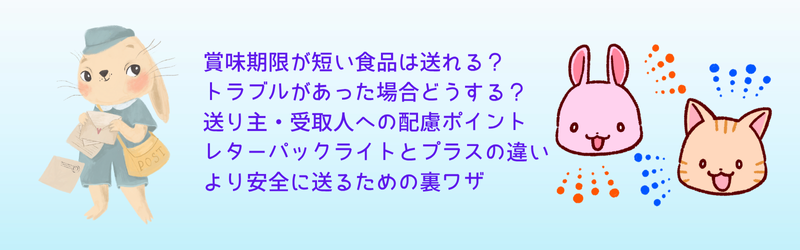
読者のみなさんから寄せられる「これってどうなの?」という疑問に、一つずつ丁寧に答えていきますね。
賞味期限が短い食品は送れる?
結論から言うと、賞味期限が短い食品は基本的にレターパックで送るのはおすすめできません。
レターパックは通常郵便扱いなので、到着まで最短でも1日~2日かかります。
特に気温の高い時期や配達に日数がかかる地域だと、食品の劣化や腐敗のリスクがグッと高まります。
どうしても送りたい場合は、「発送日を相手に伝えて早めに受け取ってもらう」「できるだけ消費期限が長いものを選ぶ」など工夫しましょう。
生ものや要冷蔵品は絶対にNGです。やっぱり安全第一で考えてくださいね。
トラブルがあった場合どうする?
万が一、食品が壊れたり水濡れしてしまった場合は、まずは送り主と受取人で状況を確認しましょう。
レターパックは基本的に「保証なし」ですが、郵便局で相談できることもあります。
配送中の事故による破損や水濡れは、原則として補償対象外です。
どうしても大切なものを送りたい場合は、「ゆうパック」など保証がある配送方法の検討もおすすめです。
「これ本当に大丈夫かな?」と少しでも心配なら、無理せず安全策を取るのが一番ですよ~。
送り主・受取人への配慮ポイント
送り主としては、品名や梱包にしっかり気を配り、「なまものではない」「常温保存可能」としっかり明記することが大切です。
また、受取人には「いつ届くか」「中身は何か」を事前に伝えておくと親切です。
食品の場合、到着後すぐに食べる予定かどうかも確認しておくと安心ですよ。
メモやメッセージカードを添えておくと、気持ちも伝わりますし、注意点も共有できます。
ちょっとした心遣いがトラブル防止につながるので、ぜひ実践してみてくださいね!
レターパックライトとプラスの違い
「ライト」と「プラス」の一番の違いは、配達方法です。
レターパックライトは郵便受けへの投函、プラスは対面での手渡し&受領印が必要です。
食品を送る場合、「対面で手渡し」のプラスの方が安心感は高いですが、料金はプラスの方が高くなります。
また、厚み制限も異なり、ライトは3cm以内・プラスはA4サイズ&4kgまで。
賞味期限や安全性を重視するなら、受取時に必ず人がいる状況(プラス)がベストですよ!
より安全に送るための裏ワザ
ちょっとした裏ワザとしては、外装の上からさらにビニール袋やラップで包んだり、防水スプレーを使うこと。
品名に「なまものではありません」「常温保存可能」と明記すると郵便局員さんも安心です。
相手が不在の場合の再配達や、宅配ボックス利用の希望を事前に伝えておくのもポイント。
あとは、「ゆうパック」やクール便など他の配送手段と迷った場合は、荷物の内容や距離、日数で使い分けましょう。
「これだけやれば大丈夫!」と思えるくらい、念入りな梱包と事前連絡が大事ですよ~!
まとめ|レターパック 食品 書き方を押さえて大切な気持ちを届けよう
| 見出しリンク | 内容 |
|---|---|
| 品名の具体的な書き方 | 食品名は具体的に、「なまものではない」など補足も忘れずに |
| 避けるべき表現やNGワード | 「プレゼント」「食品類」など曖昧な言葉は使わない |
| なまもの・冷蔵食品の扱い | 生ものや冷蔵・冷凍品はNG!必ず常温で大丈夫なものを |
| 宛名や注意書きの記載方法 | 品名+注意事項を明記し、気配りを伝えよう |
レターパックで食品を送るときは、「品名を具体的に書く」「なまものや冷蔵が必要な食品は避ける」「梱包を丁寧に行う」など、ちょっとした工夫がとても大切です。
曖昧な表現は使わず、受け取る相手のことを考えて細やかに準備しましょう。
分からないことがあれば郵便局の公式サイトや、信頼できる梱包資材メーカーの情報も参考にしてください。
気持ちが伝わる食品ギフトが、無事に相手へ届きますように。